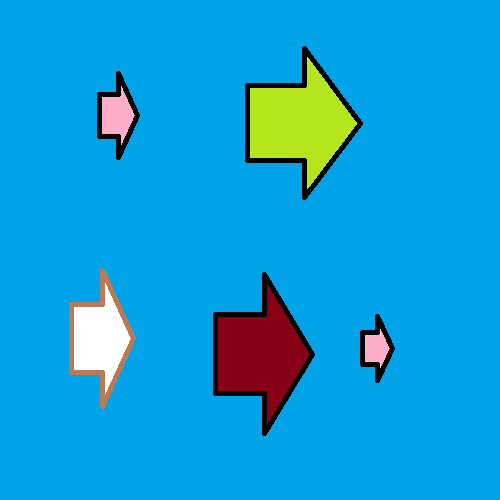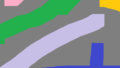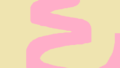一級建築士試験は、
日本で最も難関の国家資格の一つです。
合格率は例年10〜15%前後と低く、
専門学校や講座を使う人も多いですが、
「独学」で合格を目指す人も少なくありません。
独学の最大の武器は、なんといっても「過去問」です。
この記事では、実際に独学で合格した受験生の体験をもとに、
「過去問の使い方」にフォーカスした勉強法を5つ紹介します。
① 最初の3年分を“解かずに読む”
まずは直近3年分の問題を、
解かずに「読み込む」ことから始めましょう。
理由は、試験問題の「出題傾向」や「言い回し」に慣れるためです。
読み方のコツは、
「なぜこの選択肢が間違いなのか」
を自分の言葉で説明すること。
② 分野別に解くことで弱点が見える
過去問をそのまま年度ごとに解くと、知識がバラバラになります。
それよりも、「構造」「計画」「施工」など、
分野別に分類して繰り返し解くことで、
自分の弱点がはっきりします。
たとえば、構造力学が苦手な人は、
その分野の過去10年分だけを集中して演習してみましょう。
③ 解説付きの市販本は必須
市販されている「過去問集」は、
必ず解説が詳しいものを選びましょう。
おすすめはTACや総合資格学院が出している赤本・青本シリーズ。
単なる答えの羅列ではなく、
「なぜそうなるか」まで書かれている本が理解の助けになります。
④ 間違えた問題は“ノート化”する
間違えた問題は、答えを覚えるのではなく
「自分の誤解」に気づくことが重要です。
そのため、
解いた後は「なぜ間違えたか」「どう覚え直すか」を
まとめる「間違いノート」を作りましょう。
試験直前に見返す教材としても役立ちます。
⑤ 模試ではなく“本番”を想定した時間配分で
試験本番では、時間との戦いになります。
過去問を解くときは、
1問○分で解くと時間を決めて取り組むクセをつけましょう。
全体で150分の試験なら、
1問にかけられる時間は約3分。
このタイムマネジメントは、模試よりも過去問演習で磨かれます。
まとめ:過去問は最高の教科書
過去問は、建築士試験を知るうえで最強の教材です。
独学でも合格できる人がいるのは、
「過去問を徹底的に活用している」から。
使い方を間違えなければ、
どんな受験参考書よりも実戦的な学習ができます。