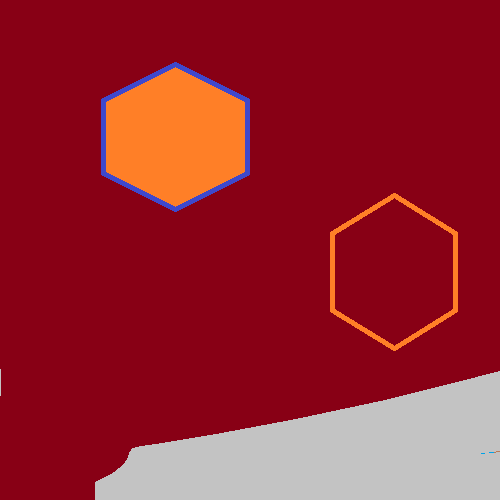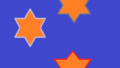建築設計の現場では、
日々さまざまな課題や変更に直面します。
しかし、私が経験したあるトラブルは、
今でも設計者人生の中で最も大きな衝撃として記憶に残っています。
それは、一級建築士になって初めて担当した公共施設のプロジェクトで起きた、
「設計図の全修正」という出来事でした。
プロジェクトの概要
私が設計主任として初めて任されたのは、
市の文化施設の新築工事。
図書館と市民ホールを併設した複合建築で、
敷地面積は3,000㎡超。
市民の生活に密着する公共施設であり、
プレッシャーも大きいプロジェクトでした。
設計チームには私のほかに若手2人、
外部の構造・設備設計者も含めて進行しており、
基本設計、実施設計と順調にステップを踏んでいました。
トラブルの発端は“用途地域の見落とし”
実施設計がほぼ完了し、
いよいよ確認申請の提出を目前に控えていた頃、
担当した行政の都市計画課から一本の電話が入りました。
「敷地の一部が第1種低層住居専用地域にかかっていますが、この建物はその用途に合致しません。」
一瞬、頭が真っ白になりました。
なんと、敷地の境界が地目変更中だったため、
設計初期の法規チェック時に用途地域の誤認が発生していたのです。
確認申請に入る直前の段階で、
施設の一部がその地域制限に抵触していることが発覚しました。
設計図の“全やり直し”
用途地域の制限により、
建物の高さ制限、容積率、建ぺい率が大きく変わることに。
結果として、建物の配置・断面計画・構造計算・空調ルートまで、
すべてを見直す必要が生じました。
納期はすでにギリギリ。
市の予算年度にも関わるため、
遅延は絶対に許されない
プロジェクト全体が非常に緊迫した空気に包まれました。
私はすぐにチームメンバーを集め、
徹夜作業の連続で図面の修正に取りかかりました。
構造設計者とも毎晩Zoom会議で修正点をすり合わせ、
行政と何度も協議しながら、一から再構築していきました。
信頼を失わないために
正直、責任の重さに押しつぶされそうになりました。
自分の確認ミスで、
チームにもクライアントにも大きな迷惑をかけてしまったことへの罪悪感。
設計者としての信用を失うのではないかという不安。
しかし、私が意識したのは「逃げない」こと。
誤りは誤りとして正直に説明し、
どうリカバリーするかに全力を尽くす。
それが唯一、信頼をつなぐ方法だと信じて行動しました。
結果的に、2週間で全図面を修正し、
ギリギリのタイミングで確認申請に滑り込むことができました。
行政との関係も悪化せず、
工期も守ることができたのは、
チーム全員の支えがあってこそです。
この経験から得た教訓
このトラブルで、私は設計者として最も大切なことを学びました。
• 法規チェックは初期段階で何重にも確認すること
• 不確かな情報は“都合よく”解釈しないこと
• トラブル時ほど、誠実な対応が信頼につながること
建築は「モノをつくる仕事」であると同時に、
「人との信頼をつくる仕事」でもあると、
あらためて実感した出来事でした。