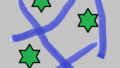一級建築士として働く中での苦労は、試験合格後も続きます。
特に設計・監理業務においては、技術的な問題だけでなく、
クライアントやチームとのコミュニケーション、現場の管理など、さまざまな課題に直面することが多いです。
以下に具体的な例を交えつつ、苦労した経験をいくつか挙げてみます。
1. クライアントの要望と実現可能性のバランス
クライアントからの要望は時に非常に高いものですが、それを実現するためには予算や敷地条件、法規制などが大きな制約となります。
特に予算が限られている場合、理想と現実のギャップに悩むことが多いです。
あるクライアントから、非常に斬新で美しいデザインのビルを依頼されました。
しかし、予算がかなり限られており、最初に考えていたデザインでは予算オーバーとなることが判明しました。
そこで、デザインを変更せずにコストダウンを図るため、材料や施工方法を見直し、
建築設備を調整するなどの工夫が必要でした。
このような時、クライアントに納得してもらえる形で現実的な提案をするためには、
技術的な知識だけでなく、コミュニケーション能力が求められます。
クライアントとの信頼関係が非常に大切だと感じました。
2. 現場監理の大変さ
建物の設計だけでなく、施工中の現場監理も一級建築士の重要な仕事です。
現場では思いもよらない問題が発生することがあり、予期しない事態への対応が求められます。
あるプロジェクトで、現場で施工業者が間違った方法で配管工事を進めてしまい、完成間近でそれが発覚しました。
そのため、設計通りに配管を通すためには、部分的に壁を壊して再工事をしなければならない状況になり、大きなコストと時間がかかることが判明しました。
この問題に対して、私は即座に施工業者と打ち合わせを行い、最適な解決策を提案しましたが、
現場での調整が非常に大変で、監理としての責任を痛感しました。
3. 法規制や行政との調整
一級建築士として、法令や規制に則った設計を行うことは必須ですが、時にそれらの規制が設計の自由度を制限することもあります。
また、行政との調整が必要な場合も多く、スムーズに進まないことも少なくありません。
あるプロジェクトで、都市計画法に基づいて、建物の高さ制限がありました。
最初の設計案では高さ制限に違反していたため、再設計が必要になりました。
その後、何度も行政との調整を重ね、法的に問題のない範囲で設計を変更し、ようやく承認を得ることができました。
このように、法規制を守りながらデザイン性を維持することは非常に難しく、計画段階から行政との対話をしっかりと行う重要性を感じました。
4. チームのリーダーシップ
一級建築士としては、設計の方向性を決定するだけでなく、プロジェクトチームを牽引する役割も担います。
複数のスタッフや専門家と協力して、スムーズに進行させることが求められますが、
メンバー間の意見の食い違いやスケジュールの調整が難しいこともあります。
大規模な商業施設の設計プロジェクトで、デザインに関する意見が設計チーム内で分かれたことがありました。
一部のメンバーは、より斬新で実験的なデザインを提案し、別のメンバーは実用性を重視して慎重な案を出しました。
そのため、プロジェクトの進行が滞りがちになり、最終的にどちらの方向性に進むべきかで悩みました。
最終的には、両方の意見をうまく融合させる形で解決しましたが、チームをまとめる難しさを痛感しました。
5. 納期と品質のバランス
建築業界では納期が非常に厳しく、スケジュール通りに進めることが求められます。
しかし、納期に間に合わせるために品質が犠牲になることがないよう、常に両者のバランスを取る必要があります。
ある案件では、クライアントから
「できるだけ早く完成させて欲しい」と強く要望され、納期がかなり前倒しになりました。
そのため、設計から施工に至るまで、急ピッチで進めなければならなかったのですが、
急ぐあまり品質や詳細が疎かにならないように気を付けました。
しかし、現場でいくつかのミスが発覚し、その修正に時間がかかるなど、最終的に納期ギリギリでの完成となり、大きなプレッシャーを感じました。
一級建築士としての仕事は、単に設計だけではなく、多方面にわたる調整や対応が求められるため、日々の業務の中で常に課題に直面します。
しかし、それらを乗り越えた先に、完成した建物が実際に使われる瞬間の達成感や、クライアントの満足そうな顔を見ることができるのは、この仕事の大きな魅力でもあります。