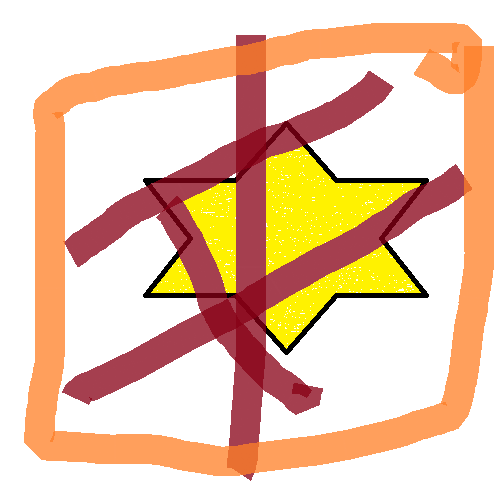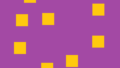二級建築士に合格した後、一級建築士の試験で苦労した経験について、具体的にどのような点が大変だったかお話ししますね。
1. 試験範囲の広さと深さ
二級建築士の試験範囲は住宅や小規模建築に特化しているため、
比較的限られた知識で対応できますが、一級建築士になると、その範囲が広がり、商業施設や公共施設など、大規模な建築に関する知識も求められます。
特に法規や構造の理解が深く問われるので、全体像を把握するのが非常に難しかったです。
法規に関する問題では、例えば耐震基準や消防法、建築基準法の細かい部分まで覚えておかないと解けない問題が出題されました。
二級建築士ではそこまで細かく突っ込んだ内容はなかったので、
試験勉強のスタート段階で「こんなに広い範囲をカバーしなければならないのか」と実感して、圧倒されました。
2. 製図試験の難易度
一級建築士の製図試験は、二級建築士のものに比べて格段に難易度が高いです。
特に、与えられた敷地条件や制約を元に、機能的かつ現実的な設計を行うことが求められます。
製図の精度も重要で、図面のミスや寸法のズレなどが減点対象になります。
一級建築士の製図では、大規模な施設の設計を求められますが、
敷地の制約や構造の条件をうまく考慮しながら設計するのが本当に大変でした。
時間内に仕上げること自体も難しいし、提出物の精度を上げるために何度も練習を繰り返しました。
3. 学習時間と計画の立て方
二級建築士に合格した後、かなりの時間を一級建築士の勉強に充てる必要がありました。
独学ではなく、専門の予備校や参考書を使って効率的に学ぶ必要がありましたが、
独学だとどうしてもモチベーションを保つのが難しく、
試験直前まで学習計画に悩んだこともあります。
予備校に通っていたものの、仕事との両立が大変で、
毎日数時間の勉強時間を確保することが難しかったです。
また、仕事で得た実務経験があるとはいえ、
試験で求められる知識は実務とは少し違っていたので、改めて一から勉強する必要がありました。
4. 合格までのプレッシャー
一級建築士の試験は、合格率が低いこともあり、プレッシャーが大きかったです。
特に製図試験と口述試験が残っている段階で、
「これで落ちたらどうしよう」
と不安が常に付きまといました。
二級建築士に合格したことで一定の自信はあったものの、
一級建築士の壁は高く、精神的に追い詰められた時期もありました。
試験結果が発表された時には、無事に合格できたことが嬉しくもあり、
ほっとした瞬間でもありました。
しかし、その後のプレッシャーを乗り越えることが、最も大きな試練だったと感じています。
一級建築士に合格した瞬間は、言葉では表しきれないほどの達成感と安堵感が入り混じった気持ちでした。
何ヶ月、いや、何年にもわたる努力が実を結んだ瞬間で、正直、驚きと喜びでしばらく動けなかったくらいです。
試験のプレッシャーや勉強の厳しさがあったので、
合格発表を見た瞬間は「ついに終わった!」という安心感が一番強く感じられました。
長い間、仕事や生活の中で常に試験のことを意識していたので、
ようやくその重圧から解放されたことが一番大きかったです。
試験勉強を通して、たくさんの時間を割き、何度も壁にぶつかりながらも乗り越えてきたことを思い返しました。
特に製図試験は、合格するために本当に多くの努力が必要でした。
その全てが無駄ではなかったと実感し、達成感が込み上げてきました。
仕事との両立や勉強時間の確保が大変だったので、
合格発表を見た時は「やっと一息つける」と、ほっとした気持ちが強かったです。
まるで重い荷物を下ろしたような感覚で、緊張の糸が切れた瞬間でした。
自分だけでここまで来たわけではなく、周りの支えがあったからこその合格だと感じました。
家族や友人、職場の同僚の理解や応援があったからこそ、
最後まで諦めずに頑張れたんだと思います。
そういった人たちへの感謝の気持ちが溢れました。
もちろん、合格した瞬間は喜びが先行しますが、同時に
「これからどんな建物を作っていけるのだろう」
と、次のステップに対する期待や目標も感じました。
この資格を持って、どんな仕事に挑戦できるのか、自分が設計したい建物のビジョンが少し見えた瞬間でもありました。
あの瞬間の気持ちは、今でも鮮明に覚えていて、次のステップに向けて新たなモチベーションとなっています。