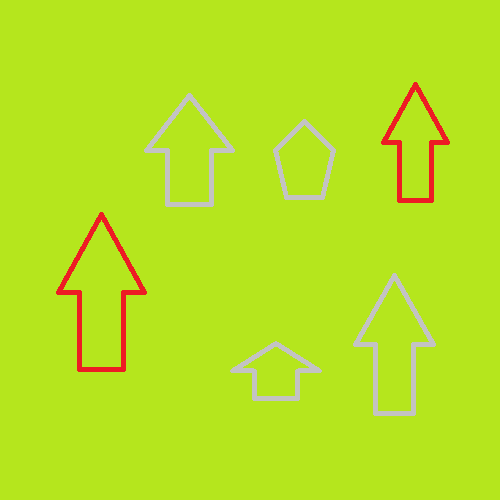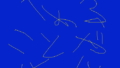はじめに
今回は設計事務所の経営者について書いていきたいと思います。
一概にこういう人が悪い!こういう人が良い!というような意見ではありません。
なので、皆様が勤めている会社に1つでも当てはまっていたら、
この会社はダメだ!と思わないように注意してください。
では、良い経営者と悪い経営者の違いを大きく分けて3つ紹介しましょう。
まずは、1つ目です。
1.心強くない。人のせいにする。
これは経営者に対する従業員の思いや信頼に関わる問題です。
従業員を信頼して仕事をまかせる。ということは経営にとって良いことです。
しかし、人間は誰しも失敗やミスをします。
その際に、その従業員のせいにするような経営者は信頼出来るでしょうか。
それまで信頼していたとしても、こういったことが一件あるだけで、一気に経営者としての信頼を失います。
仕事を従業員にまかせるというのは責任感向上や業務レベルの向上が期待できます。
だからといって放置してはいけません。
なにもアドバイスや進捗状況を聞かずに、ミスをしたら従業員のせい。
こんなことは経営者としてあってはなりません。
仮に従業員にミスがあったら、自分の指導不足です。
と、頭も下げられるような経営者なら従業員も信頼し、
今後の仕事にもっと期待できるでしょう。
そして、どんなトラブルにもドンと構えて心強い経営者が私が思う理想の経営者だと思います。
続いて2つ目です。
2.従業員にビビる。判断できない。
これは1つ目と真逆と言っていいかもしれません。
従業員にビビって従業員の顔色を伺いすぎる経営者は経営者に向いていないように思います。
従業員の顔色を伺うことは絶対的に悪いことではありません。
従業員にも生活があるし、仕事でもプライベートでも悩みはあります。
なので、そういったことに気づけることは、とても良い経営者です。
しかし、古株の従業員などに意見が言えない経営者もいます。
正直言って、そんな人が経営者になれるの?
という疑問が浮かぶかもしれません。
経営者といえば、自分で独立して会社を持ち、努力をして会社を大きくしてきた人なので、行動力のある度胸のある人だというイメージがあるでしょう。
確かにそういう経営者は多いです。
しかし、その経営者の会社を継いだ経営者はどうでしょうか?
日本は優秀な人間に会社を継承する場合は多くありません。
特に中小企業では、そんなケースとても少ないです。
どうしても、同族継承が多いです。
そういった継いだ経営者は、ろくに経営が出来ないパターンが多いです。
なぜなら、どうしても創業者と比べられますし、
大した仕事をしていないにも関わらずお金は貰えるからです。
先代を越えよう!会社を大きくしてやる!
そう思う2代目経営者もいるかと思いますが、先代と比べると大した意気込みではありません。
そういった2代目と話したこともありますが、
勢いは最初だけで、古株の従業員が言うことを聞かなかったり、
先代の方が良かった。などの小さいことで、心が折れて勢いを失って、会社としても悪い方向に進んでしまいます。
皆さんも一度は聞いたことがあるフレーズだと思います。
『息子になってから、あの会社はダメになったね』
こういった経営者には注意が必要です。
では、最後の3つ目を紹介しましょう。
3.従業員から尊敬されていない。
これは読んで字の如くです。
従業員から尊敬されていない経営者は、もう無理です。
ここでポイントなのは、尊敬されていない従業員の勤続年数です。
勤続年数の長い従業員が尊敬していない場合は、とてもまずい状況です。
逆に勤続年数の浅い若手や新入社員から尊敬されていない場合はなんの問題もありません。
その理由としては、若手や新入社員は会社の状況を対して理解しておらず、
自分の理想の職場やイメージだけで判断するからです。
こういったことはよくあることで気にしなくて良いです。
しかし、勤続年数が長い従業員、具体的には5年以上勤めている人の意見はとても重要です。
頭の良い従業員は、5年程度で会社を見切ることが多いでしょう。
辞める社員が、それなりに会社に貢献している場合は会社に問題があります。
こういった場合は、社歴が浅いと気づきずらい部分かと思います。
不信感というのは日々の業務の中でだんだん膨らんでいきます。
経営者の愚痴や不満と不信感は少し毛並みが違います。
こういったことは、20代の頃は私はイマイチ分かりませんでしたが、
30代にもなれば分かってきます。
以上が良い経営者と悪い経営者の違いと特徴です。
あなたの会社はいかがでしょうか?
これが全てではありませんが、これは私が長年の経験から感じたことです。
皆様の設計ライフに少しでも参考になれば幸いです。